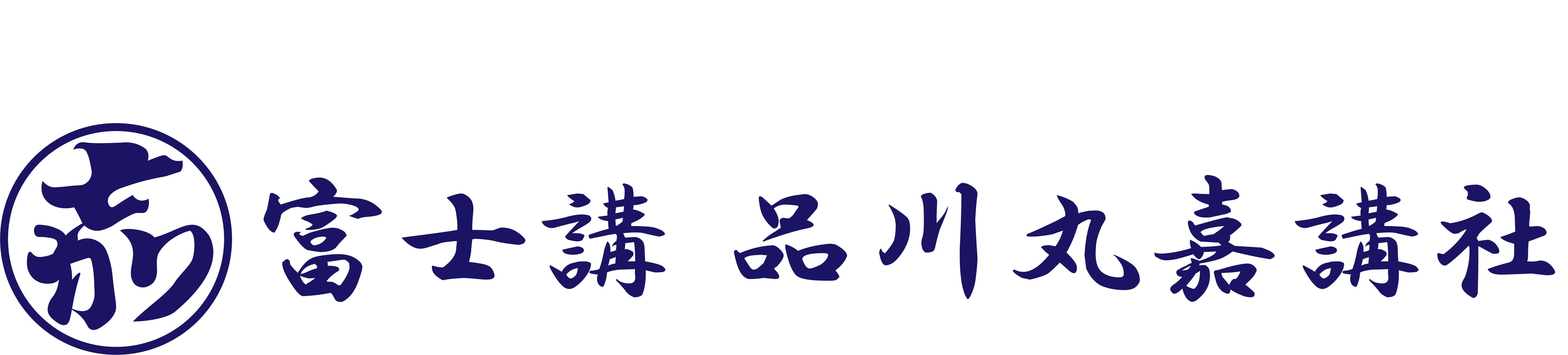1. 品川丸嘉講社の起源
富士講について言及する複数の文献では、丸嘉講の開講者は赤坂の「近江屋嘉右衛門」(寛政年間 1789年~1801年)とされています
品川丸嘉講はこの名称から、この嘉右衛門の丸嘉講の枝講と考えられます
この枝講を開講した人物は品川区発行の調査資料の冊子によると「嘉七」なる人物によって文化11年(1814年)以降に開講したのではないかと言及しています
品川丸嘉講社の講員である、北品川の呉服店「尾張屋」当主、大橋誠さんのお話によれば、
「大橋家先祖の大工 嘉七は、幕府の命令により大火で損傷した増上寺や寛永寺の修復のため上京して品川に居を構え品川丸嘉講社にかかわった」
ということでした
品川丸嘉講が嘉右衛門の丸嘉講の枝講であることを示す明確な資料は発見できませんが、「嘉七」が開講者であることを示す証言です

一般社団法人 しながわ観光協会ホームページから
https://shinagawa-kanko.or.jp/
一方、富士講の教義の系譜から見る起源としては、二代前の講元、榎本定夫さんは
「品川丸嘉講は食行身禄の三女、お花さんの系譜」
と話しています
しかしながら、嘉右衛門の丸嘉講は食行身禄の次女、万(まん)の系譜とする文献が多く、講名以外の共通点は少ないと感じます
いずれにしても品川丸嘉講は嘉右衛門の丸嘉講の枝講と考えられます
それにしても、なぜ品川に赤坂の富士講の枝講があるのか、嘉右衛門と嘉七は、どこで、どのように、繋がるのかを示す資料がどこかにあることを期待します
2. 沿革
| 文化11年 | 開講 |
| 年代不詳 | やませいもと講(と推定)を二代目嘉七が品川丸嘉講に吸収合併(大橋誠さん談) |
| 明治2年 | 品川富士を築造 |
| 明治5年 | 神仏分離政策で破壊された品川富士を再築 |
| 昭和53年 | 品川区、品川富士を有形民俗文化財第一号に指定 |
| 昭和61年 | 品川区、品川神社富士塚山開き行事を無形民俗文化財(風俗慣習)第一号に指定 |
3. 歴代先達
品川丸嘉講社の先達として氏名がわかっているのは明治以降で、品川丸嘉講社に伝わる制作年代不詳、お伝え印刷本(手書きの複製印刷)に昭和までの記録が残っています
品川丸嘉講社<明治以降の先達氏名>
| 1代目 | 大嘉多久美藤原重徳 |
| 2代目 | 玉井半次郎 |
| 3代目 | 大嘉嘉七 |
| 4代目 | 榎本六兵衛 |
| 5代目 | 榎本市太郎 |
| 6代目 | 木氏松太郎 |
| 7代目 | 榎本豊吉 |
| 8代目 | 榎本新三郎 |
| 9代目 | 伊藤生司 |
| 10代目 | 牛田八郎 |
| 11代目 | 榎本治郎(昭和63年) |
| 12代目 | 榎本貴 |
| 13代目 | 鈴木康司 |
| 14代目 | 柏木悟 |